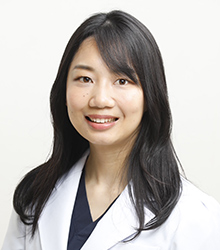足首の捻挫、様子見は危険?受診を迷ったら
はじめに
足首を捻ってしまった経験は、多くの方がお持ちではないでしょうか。「ちょっと痛いけど歩けるから大丈夫」「時間が経てば治るだろう」と軽く考えてしまいがちな足首の捻挫ですが、実は見た目以上に深刻な状態である可能性があります。
適切な診断と治療を受けずに放置してしまうと、慢性的な痛みや関節の不安定性、さらには変形性関節症といった後遺症につながる可能性があります。また、一度捻挫した足首は捻挫を再発しやすく、日常生活の質を大きく低下させることにもなりかねません。
本記事では、SBC横浜駅前整形外科クリニック院長の川﨑成美が、足首の捻挫について詳しく解説いたします。軽く見えても危険な症状の見極め方、受診すべきタイミング、そして適切な応急処置について、医学的根拠に基づいてわかりやすくお伝えします。
足首の捻挫とは?基本的な知識
捻挫の定義と仕組み
足首の捻挫とは、関節に力が加わって起こるケガのうち、骨折や脱臼を除いたもので、レントゲン検査で異常が認められない関節のケガを指します。具体的には、関節を支えている靭帯や腱などの軟部組織、そして関節軟骨や半月板といった軟骨組織が損傷した状態です。
靭帯は、骨と骨をつないで関節を安定させる役割を持つ、いわばゴムバンドのような組織です。捻挫では、このゴムバンドが伸びたり、部分的に、あるいは完全に切れてしまうことがあります。足首は私たちの体重を支え、歩行や運動を可能にする重要な関節であるため、この損傷は日常生活に大きな影響を与える可能性があります。
軽く見えても危険な捻挫の症状
見た目に騙されやすい軽度の捻挫
「歩けるから大丈夫」「少し痛いだけだから」と軽く考えてしまいがちな捻挫 の症状ですが、実は見た目以上に深刻な状態である可能性があります。特に軽度の捻挫では、靭帯が少し伸びた状態であり、少し痛みや腫れがあるものの歩行は可能です。日常生活にはそれほど支障がないため、つい放置してしまいがちですが、実は慢性化のリスクが潜んでいます。
痛みを感じにくい部位もあるため、「あまり痛くないから大丈夫」と考えてはいけません。多くの捻挫では、ケガをしてから1~2ヵ月くらいもすると強い痛みは取れ、日常生活に支障はなくなります。しかし、その後はスポーツ活動などで負担が加わったときの痛みや腫れ、ぐらつき感などが主な症状として残ることがあります。
重症度による症状の違い
捻挫の重症度は、靭帯の損傷の程度に応じて、軽度、中等度、重度の3段階に分類されます。以下の表で、それぞれの症状の違いを詳しく見てみましょう。
| 重症度 | 靭帯の状態 | 主な症状 | 歩行への影響 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 軽度(Ⅰ度) | 靭帯の軽微な損傷(伸びる) | 軽い痛み、軽度の腫れ | 歩行可能だが違和感あり | 普段通り生活できることが多い |
| 中等度(Ⅱ度) | 靭帯の部分断裂 | 強い痛み、明らかな腫れ、内出血 | 歩行困難、跛行 | 日常生活に支障が出る |
| 重度(Ⅲ度) | 靭帯の完全断裂 | 激しい痛み、著明な腫れ、広範囲の内出血 | 歩行不能 | 日常生活に大きな支障 |
慢性化のリスク
適切な捻挫の治療を受けずに放置すると、将来的に足関節不安定症や変形性関節症といった慢性的な問題が生じる可能性があります。靭帯が緩んだまま動くことで、関節に負荷がかかり続けるため、足首を内側に捻らなくても痛みが引かない状態となることがあります。
受診すべき症状の見極め方
緊急受診が必要な症状
足首の怪我をした際に、以下の症状がある場合は緊急で整形外科を受診する必要があります。
歩行不能は最も重要な指標の一つです。足首に体重をかけることができない、または歩行時に激痛が走る場合は、重度の靭帯損傷や骨折の可能性があります。
著明な変形が見られる場合も緊急での受診が必要です。足首の形が明らかに変わっている場合は、骨折や脱臼の可能性が高く、即座に医療機関での診察を受けることが推奨されます。
早期受診が推奨される症状
緊急性は低いものの、以下の症状がある場合は早期の受診を検討するとよいでしょう。
中等度以上の腫れが見られる場合、特に受傷後数時間で足首全体が腫れ上がる場合は、靭帯の部分断裂以上の損傷が疑われます。また、広範囲の内出血がある場合も同様です。
関節の不安定感も重要な指標です。足首を動かした時にぐらつく感じがする、踏ん張りが利かない感じがする場合は、靭帯の機能が著しく低下している可能性があります。
48時間以上続く強い痛みも受診の目安となります。適切な応急処置を行っても痛みが改善しない場合は、専門的な診断と治療が必要です。
受診を迷った時の判断基準
捻挫をして病院に行くべきかどうか迷った時は、以下の基準を参考にしてください。
「様子を見ても大丈夫」と判断できるのは、軽度の痛みと腫れのみで、歩行に大きな支障がなく、時間の経過とともに症状が改善傾向にある場合です。ただし、この場合でも適切な応急処置は必要です。
一方、「受診が必要」と判断すべきなのは、上記の症状がある場合、48時間以上症状が改善しない場合、または症状が悪化している場合です。特に、過去に同じ足首を捻挫したことがある方は、再発のリスクが高く、軽度に見えても実は重篤な損傷を起こしている可能性があるため、早めの受診をお勧めします。
捻挫の応急処置と治療法
RICE処置の重要性
足首の捻挫が発生した直後の応急処置として最も重要なのが、RICE処置です。RICE処置とは、Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の4つのステップの頭文字を取ったもので、国際的に推奨されている応急処置法です。
Rest(安静)、痛む場所を動かさず、なるべく安静に過ごします。Ice(冷却)、氷や冷水で患部を15分程度冷やし、1時間ごとに繰り返します。Compression(圧迫)、弾性包帯で患部を適度に圧迫し、Elevation(挙上)、患部を心臓より高い位置に保ちます。これによって著しい腫脹を避け、痛みを軽減させることができます。
保存的治療とリハビリテーション
軽度から中等度の捻挫 の治療では、多くの場合保存的治療が選択されます。損傷の程度に応じて1-4週間程度の固定を行い、痛みと炎症を抑えるための薬物療法を併用します。
リハビリテーションでは、関節の可動域回復と筋力強化を段階的に実施します。急性期では疼痛の緩和、回復期では関節の動きの改善、機能回復期ではバランス訓練や敏捷性を養う訓練を行い、日常生活やスポーツ活動への復帰を目指します。
手術治療
非常に稀ですが重度の靭帯損傷や慢性的な不安定性がある場合は、靭帯修復術や靭帯再建術などの手術的治療が検討されることがあります。近年では関節鏡を用いた小切開手術が主流となっており、回復が早くなっています。治療の経過次第で手術が必要な場合には、横浜市内の連携病院をご紹介いたします。
まとめ
足首の捻挫は、「軽いケガ」として軽視されがちですが、適切な診断と治療を受けずに放置すると、深刻な後遺症を残す可能性がある重要な外傷です。
重要なポイント
早期の適切な対応が重要です。受傷直後のRICE処置は、その後の回復に大きく影響します。
症状の見極めが必要です。歩けるからといって安心せず、中等度以上の腫れ、関節の不安定感、48時間以上続く強い痛みなどがある場合は、必ず医療機関を受診してください。
慢性化の予防が大切です。軽度の捻挫でも、適切な治療とリハビリテーションを行うことで、慢性足関節不安定症や変形性関節症といった深刻な後遺症を回避できる可能性があります。
次のアクション
もし現在足首 痛みでお悩みの方は、まず本記事を参考にして症状の評価を行ってみてください。
受傷後48時間以内であれば捻挫の応急処置としてRICE処置を実施してください。症状が改善しない場合や、本記事で示した受診基準に該当する場合は、迷わず整形外科を受診することをお勧めします。
SBC横浜駅前整形外科クリニックでは、足首の捻挫の診断から治療、リハビリテーション、そして予防まで、包括的なサポートを提供しております。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
よくある質問